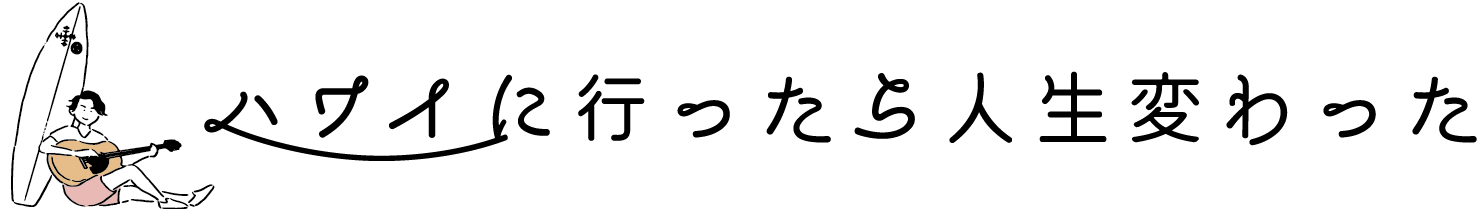金融資産構成を日本・アメリカ・ユーロエリアで比較すると、日本人が株式投資に対して、あまり関心が高くないことが明らかになります。
日本銀行調査統計局の2020年資金循環の日米欧比較によると日本の家計における金融資産のうち、投資信託は3.4%、株式等は9.6%の構成なのだそうです。
一方、アメリカの家計は投資信託が12.3%、株式等は32.5%。そして、ユーロエリアの家計は投資信託が8.7%、株式等は17.2%とのことでした。
会社に勤めていると、そこまで深く考えずにいつの間にか株式投資を行っていることもあります。企業型確定拠出年金や従業員持株会がそうです。
今回は、株式投資の仕組みや運用中に大切なことをご案内していきます。
株式投資って何だろう

まずは簡単に株式を保有することの意味を探してみます。
株式を保有する意味は次のようなところでしょうか。
・株式は売却ができます。買った金額よりも値上がりしてるときに売却したら、儲かりますし、買った金額よりも値下がりしているときに売却したら、損をします。
・ 株主には配当金をもらう権利があります。
・ 株主として株主総会で議決権を持つことができます。
・ 会社を清算する場合、余った剰余金を受け取ることができます。
株式には、上場会社の株式と非上場会社の株式がございます。
ここで取り扱うのは上場株式ですが、非上場会社の株式も、上場会社のように株価は決算内容により変化しますし、配当金をもらう権利、議決権、残余財産の分配を受ける権利があります。
株価の決まり方

株式の価額はどのように決まるのでしょうか?
みんなが欲しがる株式、たくさん購入されている株式の価額は高くなります。
みんなが欲しくない株式、たくさん売却されている株式の価額は安くなります。
非上場会社の株式の評価方法を参考にすると、どのような会社の株価が高くなるのか見えてくるので簡単に紹介します。
非上場会社の株式は、上場会社の株式のように取引市場で毎日売買されているわけではないので、直近の決算数値を使って、税法で決められた計算方法で株価を算出します。
そのときに使う項目が、利益、配当、純資産の金額です。計算方法について、詳細は記載しませんが、主には、これら3つの金額を同様の事業を行っている上場会社と比較して、計算していきます。
そのため、利益が出ている会社、配当金を多く出している会社、純資産(資産−負債)が多い会社の株価は高くなりますし、利益が出ていない会社、配当金が少ない会社、純資産(資産−負債)が少ない会社の株価は低くなります。
上場会社は、取引市場で毎日、株式が売買されているので、利益、配当、純資産(資産−負債)の金額の大小だけが株価を上下させるわけではなく、経営者のコメント、有名な投資家の投資行動、政府の政策など、将来、利益、配当、純資産(資産−負債)がどうなりそうかという予想や投資家の期待が株価に影響してきます。
株価の変化
私自身が従業員持株会を通じて保有する株式を例にとって、株価の変化がもたらすことをご案内していきます。
従業員持株会は勤める会社の株式を会社から奨励金をもらいながら、毎月一定額を購入していく制度であります。
株式投資への理解を深めて自ら行動をおこすというよりは、会社の方針として、従業員の財産形成の取り組みとして、あまり深く考えずに、従業員持株会へ加入している方も多いと思います。
私は従業員持株会へ加入し、毎月5,000円、会社から250円の奨励金を受けながら、総額約30万円、私が勤める会社の株式を購入してきました。
約30万円支払ってきたことで保有している株式数は151株です。
今の株価は1,200円なので、私の保有している株式の価額は、151株×1,200円=181,200円です。
そうなんです、今保有株式を売却したら、30万円−18.1万円=11.8万円、損してしまいます。
売却せずに持ち続け、株価が1,986円(30万円÷151株)を超えてきたときに売却すれば、支払ってきた金額よりも売却して得る金額の方が多くなります。
株価が2,500円を超えていた時期もありましたので、そのときに毎月ドル・コスト平均法※で定期的・継続的に購入していた分が大きな損になっているのでしょう。
※ ドル・コスト平均法とは、一定金額で定期的・継続的に投資する方法です。価格が高い時は購入数量を少なく、安い時には多く購入します。
主な株式投資の選択肢
それでは、株式投資が関係する選択肢を確認していきましょう。ここでは株式投資の種類を6つあげます。
01. 個別上場株式保有
02. 従業員持株会
03. 投資信託
04. NISA、つみたてNISA
05. 企業型確定拠出年金
06. 個人型確定拠出年金(iDeCo)
07. 非上場株式の保有
全て取り組むことがすごいわけではありません。それぞれメリットもあればデメリットがあります。
一つひとつ確認していきます。
01. 個別上場株式保有
上場会社の株式を個別に保有する株式投資です。
02. 従業員持株会
従業員持株会は勤める会社の株式を会社から奨励金を受け取りながら、毎月一定額を購入していく制度です。
従業員持株会は、勤める会社の株式を会社から奨励金を受け取りながら、毎月一定額を購入していく制度です。 株式投資への理解を深めて自ら行動をおこすというよりは、会社側の従業員の財産形成として、あまり深く考えずに、従業員持[…]
03. 投資信託
投資信託は、多くの投資家から集めた資金を1つにまとめて株式や債券など異なる銘柄や資産に分散して投資する仕組みです。
どのような株式や債券に投資するかを運用の専門家に任せます。
投資信託は、多くの投資家から集めた資金を1つにまとめて株式や債券など異なる銘柄や資産に分散して投資する仕組みです。 どのような株式や債券に投資するのかを運用の専門家に任せます。 多くの投資家から集めた資金をまと[…]
04. NISA、つみたてNISA
NISAとつみたてNISAは、株式投資を行う際の税金の優遇制度です。税金の優遇は手元に残るお金を増やしてくれます。
株式投資を行う際にかかる税金を、NISAやつみたてNISAの仕組みを使えば、支払わなくても良いのです。
ただし、無制限に認めているわけではなく、利用金額の上限が決まっていたり、利用の条件が定められています。
しかし、それらの条件をクリアするのは決して難しいものではありません。
NISAとつみたてNISAという言葉を聞いても、自身とは関係ないと考えて、仕組みを知ろうとしてこなかった方に向けて、あらためてNISAとつみたてNISAの仕組みをご案内していきます。 NISAとつみたてNISAは、株[…]
05. 企業型確定拠出年金
企業型確定拠出年金制度は、勤める会社が負担する事業主掛金を受けて、加入者が積立金の運用方法(預貯金・信託・株式・生命保険・損害保険等)を選定し、60歳以降にその運用実績を給付額として受け取れる制度です。
実際に確定拠出年金は、原則、60歳まで中途解約はできません。
加入者が60歳になるまで、払い込むお金は運用されながら、拘束され続けるのです。
「勤める会社の企業型確定拠出年金に加入してるけど、どういう仕組みだったのかを覚えていない」、「年に1度、運営管理機関からのお知らせを見るたびに思い出すだけ」、そういった方が多いと思います。 加入時の説明会では、生活の[…]
06. 個人型確定拠出年金(iDeCo)
個人型確定拠出年金制度は、iDeCoの愛称で呼ばれ、企業型確定拠出年金の個人版です。
将来、毎年定期的・継続的に給付が受けられることを目的としています。国民年金、厚生年金に加えて、将来の自分への備えです。
確定拠出年金制度は、加入者が積立金の運用方法(預貯金・信託・株式・生命保険・損害保険等)を選定し、60歳以降にその運用実績を給付額として受け取れる制度です。 確定拠出年金には、個人型と企業型があります。個人で取り組む[…]
07. 非上場株式の保有
非上場株式はいつでも売買できない点で上場株式と異なります。
価額は税法で定められた方法に従い、決算書の数値に基づき算定されます。
事業を立ち上げた創業者や親族、従業員や取引先が保有していることが多いです。
インサイダー取引
投資家の投資判断に重大な影響を与える未公表の事実を知って、自身の利益を図り、株式の売買を行うことをインサイダー取引といいます。
その事実を知らない投資家が不利な立場になることから、金融商品取引法で禁止されています。インサイダー取引は、ご自身、そして会社を思わぬ窮地に追い詰めることになります。
証券会社、銀行、コンサル、税理士など、インサイダー取引を防止するために勤めている会社から、上場株式の投資を制限されている方は多いと思います。
会社の朝礼や研修で、インサイダー取引が会社だけでなく自分自身をも窮地に追いやってしまう話や自身で投資を行わなくても家族や友人にインサイダー情報を共有して、その家族や友人がインサイダー取引を行った場合にも罰則の対象になるといった話を聞き続けていると、株式投資に対して行動することにどんどんネガティブになっていきます。
私自身も今の会社に入社して8年間、株式投資の情報集めを敬遠していました。
インサイダー取引を理由に株式投資の情報に触れることを避けていたため、自身にできることを探して株式投資を行っている方との差が広がっていました。
投資信託は原則として、インサイダー取引にはあたりません。多数の銘柄に投資するためです。また、従業員持株会もインサイダー取引の対象外です。
運用中に大切なこと

運用状況をすぐに確認できる環境を整えることが大切だと考えています。
日々、一喜一憂するような投資ではなく、長い目線で考えている方も思い立ったとき、すぐに運用状況を確認できる環境を作って欲しいです。
運用状況を確認する習慣があると、投資のことを自然と考えるようになります。思い付いた情報を探してみたり、方針を転換してみたり、変化が起きたときの対処方法をシミュレーションしておきます。
スマートフォンの待ち受け画面に投資関連のアプリをまとめたり、ブックマークを登録したりと、思い立ったらすぐに運用状況へアクセスできるようにしておきます。
会社のキャビネットはキレイにしていても、家の書類は整っていない方は多いと思います。運用状況をいつでも確認できるようにしておくという目的でいえば、家の書類も整理できているようにしましょう。
日頃から資産状況に触れておくと、そんなに値動きもしないから、長きに渡って投資できていること、また自身の投資の軸やプランを都度思い出すことができるために、変化が起きた時に慌てないのだと思います。
いくら投資に回せば良い?
ご自身の中でいくらなら投資に回せるのか、明確にしておきましょう。これも自身の財産状況や収入と支払の状況を把握できていると答えが出しやすいです。
投資している資産が最悪なくなったとしても、生活はできるように準備した上で、投資を始めます。自身で事業をやっていない中で突然お金持ちになるのはやはり難しいのです。
投資を始める前に、給料の手取り額の6か月分は貯金しておきたいです。
その上で、給料の10%分は、結婚式、お葬式、里帰り、入院など、臨時出費に備えて、貯金を継続しましょう。
それでも手元に残った資金が、無理せず投資に回せる金額だと考えています。
投資に回せるお金を増やすためには、本業と向き合って収入を上げること、生活費の節約を進めて月々の支払いを抑制することが必要です。
経験上、貯金がない中で投資したり、無理して節約しすぎたりすると、自分のお金をコントロールできている状態ではないため、長続きしないように思います。
また準備が足りないと、投資とギャンブルは違うことを忘れてしまうようです。繰り返しになりますが、自身で事業をやっていない中で突然お金持ちになるのは難しいのです。
証券会社の選択方法
証券会社は株式投資のパートナーです。証券口座がなければ、株式を保有することができません。
株式投資を始めるにあたり、口座を開設する場合には、楽天証券をおすすめします。
手数料が安いこと、アプリ・webでの操作が行いやすいこと(管理がしやすい)、生活動線との連動(ほかの楽天サービスとの連携)があることがおすすめの理由です。
アプリ・webでの操作が行いやすいと書きましたが、初めて操作するときは、それでも専門用語や数値が並んでいて、不安があるかもしれません。
最初は時間がかかっても焦らず、色々な操作を行なってみてください。操作を通じて、言葉の意味やグラフの意味、便利な機能の発見ができるはずです。
おわりに
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
もし、これから株式投資を始めるのであれば、分散投資ができ、専門家に運用を任せることができて、税制優遇を受けるように、つみたてNISA経由で生活に無理のない範囲で投資信託購入から始めてみることをおすすめします。
若いうちにお金を持つことが大切です。
おじいちゃん、おばぁちゃんになって、必要以上のお金を持っても使うことができません。しかし、おじいちゃん、おばぁちゃんになったときにお金がないのはいけません。
自分が年を重ねることは、毎日にどのような影響を与えるのでしょうか。ケガをしたわけでもないのに、身体が痛くて、動くのに苦労があって、今より夏が暑かったらどうでしょうか?それでも収入を得るために外へ出掛けなければならないとしたら。
私自身、ファイナンス教室に記載してきたことを実行するようになり、心の余裕が持てるようになりました。
生活の中で毎月かかる支払いを削減して、投資をして、決して大きく給与収入が増えたわけではないのですが、支出が減って、将来の備えやお金が増えそうな期待にお金を回すことができています。
目的もなく行っていた厚生年金、企業型確定拠出年金、従業員持株会、貯金が、将来の自分の収入にどこまでプラスの影響を与えるかを正確に知ることで、今に使えるお金はいくらなのかを把握できました。
厚生年金、確定拠出年金、従業員持株会、貯金はいずれも、本業の会社にかかる仕組みです。いつの間にか、将来の準備を作ってくれたことを会社に感謝しつつ、本業を頑張ろうと思いました。
本業も辛いことがあるかもしれないけど、入社の時はやりたいと考えて進んだ道です。
人間関係で悩むことがあると思いますが、相手にも家庭があって、両親がいると考えるとイライラするのがバカバカしくなります。
本業があるのであれば、長い目で本業の収入にプラスアルファするくらいの気持ちの方がまずは良さそうです。
大きなお金を投資に回したいという方もいらっしゃると思います。そのお金を生み出すためには自らおこすビジネスが必要です。生活することも必要ですから、本業は続けつつ、副業から始めてみることをおすすめします。
今回の記事が皆さまの株式投資のお役に立てますと幸いです。
ハワイ旅行に向けてお金を節約し、投資していく方法を共有するファイナンス教室を始めます。 本業があって、1年や2年に1度ハワイ旅行に行けるような資金を作りたい方に向けた節約・家計見直し術のご案内です。 このファイ[…]